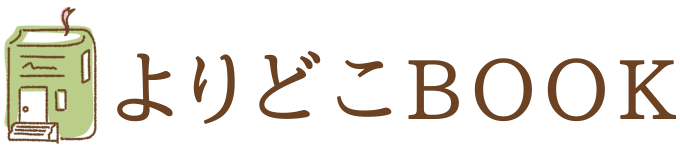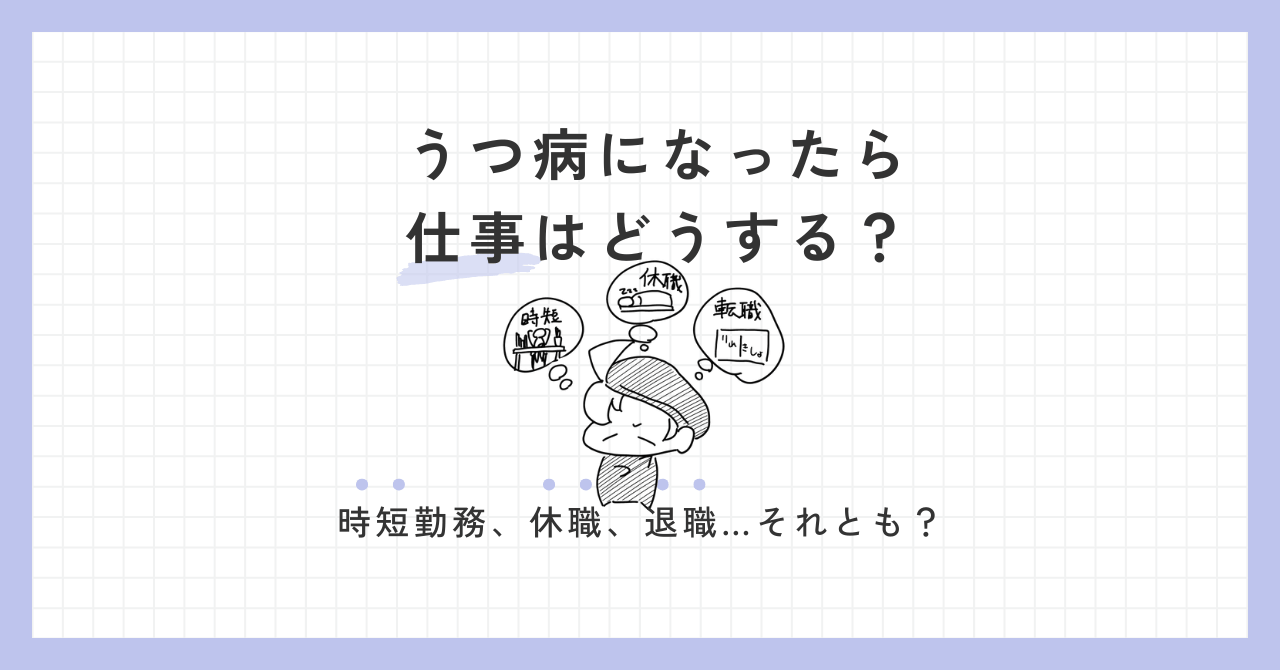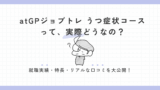社会人がうつ病と診断されたとき、真っ先に気になるのが「これからの仕事」のことではないでしょうか。
一時的に休むか、辞めて療養に専念するか、それとも無理のない範囲で仕事を続けるのか──
最善の選択肢は人それぞれで、状況や心身の状態によって変わってきます。
この記事では、うつ病と診断された後の選択肢と、それぞれのメリット・デメリット、必要な手続き、私の体験談を紹介します。
「どうしたら良いか分からない」と悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
うつ病になった後の仕事の選択肢|それぞれのメリット・デメリット

うつ病と診断されたとき、「仕事はどうしたら良いんだろう…」と悩みますよね。
ここでは、うつ病後の主な選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを一覧表で紹介します。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 休む(休職) | ・療養環境を整えやすい ・仕事によるストレスがなくなる ・給与の一部や、傷病手当がもらえる ・回復後、新しい仕事を探さなくて良い | ・安定した収入がなくなる ・仕事にブランクができる |
| 辞める(退職) | ・療養環境を整えやすい ・失業保険を受け取れる場合がある ・社会復帰までの期限がない | ・収入がなくなる ・ブランクができる ・回復後に新しい仕事を探さなければならない ・退職に伴う手続きが多い |
| 今の会社で働き続ける | ・収入がある ・ブランクの心配がいらない | ・療養環境を整えにくい ・体調が悪化し、療養期間が延びることがある |
| 転職する | ・収入がある ・今より働きやすい職場に出会える可能性がある | ・慣れない職場がストレスになることがある ・転職活動で忙しくなり、療養しづらくなる |
| 在宅フリーランスをする | ・収入がある ・体調に合わせてスケジュール調整できるので、療養環境も整えやすい ・出勤・退勤、職場の人間関係によるストレスがない | ・収入が安定しない ・PCやソフトウェアなど、仕事内容に合わせた準備が必要 |
表を見てわかるように、どの選択肢にもメリットとデメリットがあります。
ですから、「これが正解!」というものはありません。
一番大切なのは、あなたが少しでも安心できる選択かどうかです。
万が一うまくいかなくても、あとから方向転換しても大丈夫。
「今すぐに決断できないから、とりあえず今の仕事を続けてみよう」「仕事がなくなるのは怖いから、とりあえず休職しよう」と、“今できる範囲での選択”をしましょう。
▼まだ病院に行けていない人は、以下の記事もぜひチェックを。
自分にとって一番ストレスなことは、必ず避けて
あなたが安心できる選択肢なら、どれを選んでも大丈夫だと私は思います。
ただし、「自分にとって最もストレスの大きいこと」だけは、どうか避けてください。
それを無視してしまうと、うつ病の悪化につながる恐れがあります。
今の会社や部署のルール、特定の人物、会社までの道のり、仕事内容など、思い当たるストレス原因はありませんか?
もし心当たりがあるなら、それらとは距離を置くことをおすすめします。
難しいことというのは重々承知しています。
もし簡単にできるなら、そもそもあなたはうつ病になっていなかったかもしれません。
それでも、「あなたの心や体を苦しめるものは、思いきって遠ざけてもいい」ということだけは、どうか心に留めておいてほしいのです。
実際にうつ病になった私がおすすめするのは「とりあえず休職」
どうすればいいのか決めきれないときは、可能な限りの期間、いったん休職するのはいかがでしょうか。
うつ病による休職では、条件を満たせば傷病手当金がもらえるため、生活費を確保しながら心と体をしっかり休められます。
その間に、退職や転職についてじっくり考えることも可能ですよ。
選択肢に迷ったら、まずは「休む」という選択肢を持ってみてください。
【選択肢別】うつ病になった後にすることリスト
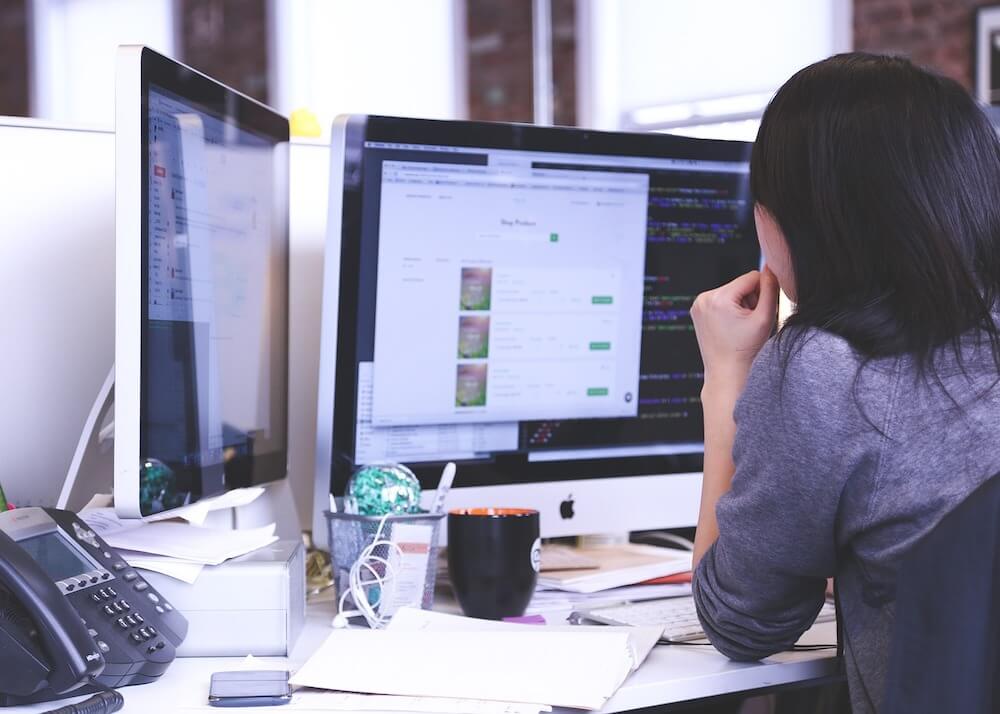
うつ病になった後にすることを、選択肢別に紹介します。
ぜひチェックリストとして活用してください。
会社をしばらく休む場合
<休職前にすることリスト>
- 直属の上司に休職したいことを伝える
- 自社の休職できる条件・可能期間・手続き方法について確認する
- 休職中の給与、社会保険の支払いについて確認する
- 医師に診断書を依頼する
- 休職手続きを行う
<休職後にすること>
- 傷病手当金の給付申請を行う(申請条件を満たしている場合)
辞めて療養に専念する場合
<退職前にすることリスト>
- 直属の上司に退職したいことを伝える
- 退職の条件・手続き方法を確認する
- 退職届を作成し、提出する
- 残っている有給休暇を退職日までに消化する
- 必要に応じて、社会保険の変更手続きを行う
- 会社に離職票を発行してもらう
<退職後にすることリスト>
- 必要であれば、市役所で国民健康保険・国民年金に切り替える
- 失業保険の給付申請をする
休職せずに今の仕事を続ける場合
休職せず、今の会社で働き続けたい場合、特に必須の手続きはありません。
ただし、うつ病中でも働きやすくするために、上司への相談をおすすめします。
<することリスト>
- (信頼できる)直属の上司に、うつ病であることを伝える
- うつ病の原因が職場にある場合、その旨も伝えておく
- 勤務形態の変更(時短、在宅など)は可能か確認しておく
- 必要に応じて、勤務形態の変更手続きを行う
今の会社を辞めて転職したい場合
<することリスト>
- 転職活動(エントリー、面接など)をする
- 内定をもらい次第、直属の上司に退職したいことを伝える
- 退職届を作成し、提出する
- 残っている有給休暇があれば、退職日までに消化する
- 社会保険の変更手続きをする
※障害者雇用で働く場合は障害者手帳が必要なので、転職活動をする前に医師に相談してください。
病気と付き合いながら働く方法がわからない、生活リズムが安定しなくて転職できる自信がないといった不安がある人は、うつ症状専門の就労移行支援【atGPジョブトレ うつ症状コース】を利用するのもおすすめです。
atGPジョブトレは1事業所あたりの平均年間就職人数が24名と、全国平均の7倍の実績を誇っています。
就職後の職場定着率も91.4%と、信頼度の高い就労移行支援事業所です。
うつ症状コースでは、長期就労に必要な障害・症状への対処法が身につきます。
同じくうつ病で悩む仲間と悩みや解決策の情報共有ができるのも、atGPジョブトレの魅力。
東京(秋葉原)・神奈川(横浜)・大阪(梅田)のいずれかに通所できる人は、ぜひ一度お問い合わせ・見学してみてくださいね。
▼口コミや実績の詳細を知りたい方はこちらの記事もチェックしてみてください。
今の会社を辞めて、在宅フリーランスをしたい場合
今の会社を辞め、在宅フリーランスになるためにすることは、『辞めて療養に専念したい場合』と同じです。
なので、退職して失業保険の手続きまで終わらせた後にすることを紹介します。
<することリスト>
- 業務委託を募集している求人サイト、またはクラウドソーシングサイトをチェックする
- 自分がやろうと思っている仕事に必要なもの(PC、ソフトウェア、スマートフォンなど)を用意する
- できそうな仕事に応募する
▼webライターに興味がある方は、こちらの記事もチェックしてみてください。
【小話】私がうつ病になってからの仕事事情
ここでは、私がうつ病になってからどのような選択をし、どんな結果を迎えたのかをお話しします。
一例として、参考にしてもらえると嬉しいです!

初めてうつ病を患った際、私はまず休職することにしました。
職場の人間関係や業務内容が原因でしたが、仕事自体は好きだったので、退職を避けたかったのです。
ところが、休職中に上司とのトラブルが発生し、症状が悪化したため最終的に退職を決意しました。(詳しくは、「入社間もないけど仕事を辞めたい人へ。自分のためになる選択をするには?」に記載の体験談をご覧ください)
休職中は傷病手当金をやりくりしながら、なんとか生活できていたのですが、問題は退職して3ヵ月後からでした。
入社して間もなかった私は失業保険を利用できませんし、傷病手当金も貯金も底をつきてしまったのです。
両親は支援金を送ってくれたため、無一文ではありませんでしたが、両親だって余裕ある生活ができているわけではありません。
1円でも良いから自分で稼がなくてはと思い、仕事を開始しました。

フルタイムはまだ難しい状態だったので、アルバイトや派遣、内職、そして在宅フリーランスを試しました。
その中で、病気に振り回されず続けられたのが在宅フリーランスでした。
出勤や直接的なコミュニケーションがなく、好きなときに作業できるという点が、私には合っていたようです。
元気を取り戻したころには、ある程度のスキルが身についていたので、転職はせずに在宅フリーランスを続けることに。
その結果、うつ病が寛解した後はしっかりと稼げて、再発した際にはすぐに休める環境を手に入れることができました。
最後に
途中にも話しましたが、あなたが最もストレスを感じることを避けられるなら、どんな選択肢を取っても大丈夫です。
忘れないでほしいのは、自分の心身第一だということ。
自分ひとりで選択できないときは、家族や友人、仕事仲間、専門の相談窓口、なんなら私でも良いので、頼って相談しても良いですからね。
あなたの辛い毎日が1日でも早く終わることを、心から祈っています。
それでは、最後まで読んでくださりありがとうございました。